|
|
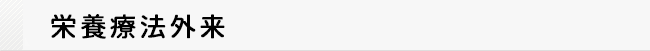 |
| |
| ���ȏЉ� |
|

��t�F�����@���m�q�i�Ȃ����܁@�������j
���m��w�̌���ɏ�������Ȉ�Ƃ���25�N�Ԍg���A�a�C�����������җl�A�Ǐ�͂��邯��Ǖa�C�ɂ͂܂������Ă��Ȃ����җl�ȂǁA��������̕��X�Ɗւ�点�Ē������ŁA�����Ă������Ƃ́A�������Â����Ă��A�ǂ��Ȃ�l�ƂȂ�Ȃ��l������Ƃ������ƁB�ȑO�͂ǂ����ĂȂ̂��ƔY�ނ��Ƃ�����܂������A�����͂����ȒP�Ȃ��ƂȂ̂ł��B���̗��R�́A�l�͂��ꂼ��Ⴄ�Ƃ������ƁB�����Đ��܂ꂽ���i�A�������A����܂ŐH�ׂĂ������́A�������A�^���K���A�������ԁA�����Ă���X�g���X�ȂǁA�S�Đl�Ƃ͈Ⴄ�Ƃ������ƁB���ꂪ�A�������Â�����Ă��ǂ��Ȃ�l�ƂȂ�Ȃ��l�����闝�R�ł��B
���̒��Ɉ��邽������̌��N���B���������H���Ă��A���P��������l�ƌ����Ȃ��l������̂��������R�ł��B�a�C�⍡����Ǐ�����P�ɓ������߂ɂ́A���Ö@����P���@��m�邱�Ƃ͕K�v�ł��B�������A����ȑO�ɁA���ꂼ��قȂ�l�̐g�̂̂��Ƃ��悭�m�邱�Ƃ��ŗD��ɂȂ�܂��B�a�@�ɍs���Ĉ�t�Ɏ��Â����Ă��炤�A�h�{�m�ɉh�{�w�������Ă��炤�A�g���[�j���O�W���ɍs���ăg���[�i�[�ɉ^���w�������Ă��炤�B�ǂ�����N�Ȑg�̂��ێ����邽�߂ɁA�K�v�Ȃ��Ƃ�������܂���B�������A���l�Ɍ��Ă��炤����ŁA�����̐g�̂̂��Ƃ�m�낤�Ƃ����A�l�C���ɂȂ��Ă��ẮA�s���̌����̉��P�ɂ͂Ȃ���܂���B
���̐f�@�ł́A�Ǐ�ɑ��Ď��Â��s�����m��w�ɉ����āA�s����Ǐ�̍��{�����ɃA�v���[�`���āA���̑Ώ����@���l���镪�q�h�{��w�A�I�[�\�����L�����[��w�̍l������������A���Â��s�Ȃ��Ă��܂��B����܂ŁA�����������Ă�����̂́A���̌����A�����킩��Ȃ����A�s����Ǐ�͂�����̂́A���N�f�f��a�@�ł̌������Ă����͂Ȃ��ƌ����A�����킩�炸���X���߂����Ă�����A�܂��A�����͌��N�łȂ�̖����Ȃ��Ǝv���Ă��邯��ǁA�g�̂̉h�{��Ԃ����͋C�ɂȂ��Ă���Ƃ������X���A���q�h�{�w�I�����ׂ邱�ƂŁA���i���܂�C�ɂ����߂Ă��Ȃ������悤�Ȍ����i�����K���A�X�g���X�A�������Ȃǁj���g�̂̉h�{��Ԃɉe�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ��������A������������邱�Ƃ��ł��邩������܂���B
���N�ŁA���C�Ȑg�̂��ێ����邽�߂ɁA�g�̂̉h�{��Ԃ𐳂����������A�X�ɉ������K�v�Ȏ��Â��邱�Ƃ��A�̒����P�A���N�ێ��ւ̋ߓ����Ǝ��͍l���Ă��܂��B�a�C�ɂȂ��Ă���a�@�ɂ�����̂ł͂Ȃ��A�s���ɂȂ�O�̐g�̂ɋC�t����悤�ɁA���җl�̎x���������Ē�����Ǝv���Ă��܂��B
|
|
| �����@���� |
|
����ȑ�w����
��w���m(����w��������Ȋw)
����w��������ȁA�s���L���a�@��������Ȉ㒷���o�āA��Ö@�l�m�P��c���N���j�b�N�Ζ�
|
| ���E�@���� |
|
����11�N
|
����ȑ�w���� |
|
����12�N
|
�s���쐼�a�@�Ζ� |
|
����14�N
|
�s�����c�a�@�� |
|
����16�N
|
����w��w�������a�@�� |
|
����25�N
|
�s���L���a�@�� |
|
����29�N
|
�s���L���a�@���Έ�t |
|
| �����@�i�� |
| ��w���m�i����w��������Ȋw�j |
| ���{���Ȋw��F����Ȉ� |
| ���{������a�w����� |
| ���{������������w����� |
| ���{��t��F��Y�ƈ� |
| �S��K�A���C�A���XRYT200���K�C���X�g���N�^�[ |
|
|
| �������\�� |
| �f�@���@���f1���� |
15,000�~ |
| �@�@�@�@�Đf(30��) |
5,500�~ |
| �@�@�@�@10�����lj����� |
2,200�~ |
| �@�@�@�@�_�H�E���f�z���̂݁@���f15�� |
5,500�~ |
| |
|
| ���q�h�{�w�̌����� 68���� |
40,000�~ |
| |
|
| ���t�R���`�]�[�� |
|
| �@�@�S��@ |
23,500�~ |
| �@�@�S��@+DHEA |
30,500�~ |
| �@�@�U��@ |
34,000�~ |
| �@�@�U��@+DHEA |
40,500�~ |
| ����DHEA-s |
18,500�~ |
| |
|
| ���[�L�[�K�b�g���� |
|
| �@�@���ǃo���A�p�l���iGBP�p�l���j |
29,000�~ |
| |
|
| �x���^�t�[�h�A�����M�[���� |
|
| �@�@�t���p�l���Q�P�X���� |
55,600�~ |
| �@�@�Z�~�p�l���P�Q�O���� |
39,300�~ |
| |
|
| �x���^�t�[�h�A�����M�[+���[�L�[�K�b�g���� |
|
| �@�@FIT132+GBP�p�l�� |
74,300�~ |
| �@�@FIT176�{GBP�p�l�� |
105,000�~ |
| |
|
| �L�Q�����{�~�l����(�є�) |
33,000�~ |
| |
|
| �L�@�_���� |
55,000�~ |
| |
|
| �����t���[������ |
49,500�~ |
| |
|
| ���f�T�v�������g�i90cap /1�������j |
15,000�~ |
| |
|
| ���f�z���i�P�Ɓj |
|
| �@�@30�� |
3,300�~ |
| �@�@60�� |
5,500�~ |
| ���f�z���i�_�H���p�j |
|
| �@�@30�� |
2,200�~ |
| �@�@60�� |
3,300�~ |
| |
|
| ���Z�x�r�^�~��C�_�H |
|
| 25g�i40���ȏ�j |
13,000�~ |
| 50g�i50���ȏ�j |
16,500�~ |
| �r�^�~��C�_�H�K�����茟��G6PD |
13,200�~ |
| �r�^�~��C�����Z�x���� |
5,500�~ |
| |
|
| �O���^�`�I���_�H�i30��/��j |
|
| 1,000mg |
6,600�~ |
| 2,000mg |
11,000�~ |
| |
|
| �}�C���[�Y�J�N�e���_�H�i30��/��j |
8,800�~ |
|
| ���q�h�{�w�I���ÂƂ� |
|
���q�h�{�w�I���ÁiMolecular Nutritional Therapy�j�́A�X�̊��җl�̍זE���x���̏�ԁA�h�{�f�̑�ӂȂǂɊ�Â��āA�h�{�w�����s���A����̉h�{�f��h�{�⏕�H�i���g�p���āA�a�C�̗\�h�E���Â��s���A�v���[�`�ł��B���̎��Ö@�́A�̓��ł̉h�{�f�̍�p���l�����āA�ʂ̎��Ìv��𗧂Ă邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��܂��B
���q�h�{�w�I���Â̎�ȃ|�C���g�́F
1.�l�ɍ��킹���I�[�_�[���C�h�Ȏ��ÁF
���җl�̐����K���A�h�{��ԂȂǂ����ɁA�X�ɍœK�ȉh�{�Ö@��v���܂��B�����Ǐ�ł��u�S�s���������̐l�v�u���t��J�������̐l�v�u�������̈����������̐l�v�ȂǁA�̂̓����̏�Ԃɉ����ĉ�����@��ς��邱�Ƃ��ł��܂��B����ɂ��A�]���̈ꗥ�ȉh�{�w�������A�����ʓI�ŋ�̓I�Ȏ��Â��\�ɂȂ�܂��B
2.�זE�@�\�̍œK���F
�͖̂�37���̍זE����ł��Ă���A���ׂĂ̐��������i�Ɖu�A�z�������A��ӁA�C���j�͍זE���ޗ������Ƃɍs�������Ő��藧���Ă��܂��B�H����T�v�������g�ɂ���ē���̉h�{�f�i�r�^�~���A�~�l�����A���b�_�Ȃǁj���[���邱�ƂŁA�זE�@�\�����P���A���N���T�|�[�g���܂��B�Ⴆ�A�r�^�~��D���Ɖu�@�\�����߂���A�I���K-3���b�_�����ǂ�}�������肷�邱�Ƃ��m���Ă��܂��B
3.�h�{���R�E�z����Q�E�ߏ�ȓőf�̑��݂������鉻�F
�x���^�A�����M�[�����E�L�@�_�����E�~�l����/�d���������E���t�z�����������E�����t���[�������Ȃǂ����p���A�]���̈�Âł̌����Ō����Ƃ��ꂪ���ȁu�@�\�̒ቺ�v��u�B�ꂽ�s���v���ł��܂��B
4.�a�C�̗\�h�Ǝ��ÁF
���q�h�{�w�I���ẤA���L�̂悤�ȏǏ�⎾���̗\�h�A���Âɖ𗧂Ƃ���Ă��܂��B
| ���� |
��̓I�ȏǏ�E���� |
| ������J�E���ӊ� |
���t��J�A�ጌ���A�~�g�R���h���A�@�\�ቺ |
| �������ǁE���ȖƉu���� |
�O���e���s�ρA�������ُ�A�_���X�g���X |
| �A�g�s�[�E�A�����M�[�E���ȖƉu�����E���ǐ������� |
�������A���[�L�[�K�b�g�A���ǐ��̎��̉��P |
| �����K���a�i���A�a�E�������E�����ُ�j |
�C���X������R���A�������ǁA�~�g�R���h���A��� |
| PMS�E�X�N����Q |
�����z�������̗���A�̋@�\�⒰�����̉e�� |
| �s�D�E�D���T�|�[�g |
�h�{���R�A�z�������̍ޗ��s���i�S�E�����E���b�_�j |
| ���g���u���i�j�L�r�E���]�E�����j |
�����t���[���A�̑��E�r���@�\�̒ቺ |
| ���B��Q�EADHD�E�w�K��Q |
�S�E�����E���b�_�E�r�^�~��B�Q�̌��R�A�]������ |
| ����̕⊮�Ö@ |
�R�_���́A��ŁA�Ɖu�����̃T�|�[�g |
| ���A�s���A�p�j�b�N��Q |
�Z���g�j���E�h�[�p�~���ቺ�A�r�^�~��B6�E�}�O�l�V�E���s�� |
5.�T�|�[�g�Ö@�Ƃ��Ă̊��p�F
���q�h�{�w�I���ẤA�]���̈�Âƕ��p���čs�����Ƃ��ł��܂��B���ÂƂƂ��ɁA�h�{��Ԃ����邱�ƂŎ��Ì��ʂ����߂���A����p���y�������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
▶ ���q�h�{�w�I���ÂŎg�����ȉ����i�F
| ��i |
���e |
| �h�{��[�i�T�v�������g�j |
�r�^�~���iC, B�Q, D, E�Ȃǁj�A�~�l�����i�����E�}�O�l�V�E���E�S�Ȃǁj�A�A�~�m�_�A���b�_ |
| �H���Ö@ |
�����l�R���g���[���A���ɂ₳�����H���A�A�����Q������ |
| �������̉��P |
�v���o�C�I�e�B�N�X�E�v���o�C�I�e�B�N�X�ASIBO�E���[�L�[�K�b�g�� |
| ��ŁE�f�g�b�N�X |
�O���^�`�I���A�r�^�~��C�A�̑��T�|�[�g�A�d�����r�o |
| �z���������� |
DHEA�E�R���`�]�[���E���z�������̌����ƒ����i�h�{�{�������P�j |
| �X�g���X�P�A |
���t�T�|�[�g�A�������P�A�}�C���h�t���l�X�ȂǂƂ̕��p |
|
| �x���^�t�[�h�A�����M�[�����Ƃ� |
|
�x���^�t�[�h�A�����M�[�����iDelayed Food Allergy Testing�j�́A�H���ɑ���A�����M�[�����������ł͂Ȃ��A�����Ԃ��琔����Ɍ����^�C�v�̃A�����M�[�����o���邽�߂̌����ł��B��ʓI�ȃA�����M�[�����͑����^�iIgE�^�A�����M�[�j�Ƃ��Ēm���A�H���ێ�㐔�����琔���Ԉȓ��ɏǏ���܂����A�x���^�A�����M�[�́A�������x��Č���邽�߁A�����̐H������肷��̂�����Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
�x���^�t�[�h�A�����M�[�́A�ȉ��̂悤�ȏǏ�������N�����\��������܂��F
�E�����s�ǂ╠��
�E���ɂ�Γ���
�E�畆�̔��]�₩���
�E��J���▝���I�Ȍ��ӊ�
�E�ߒɂ�ؓ���
�E�s���₤�Ǐ�
▶�������@�F���t����
���t����IgG�R�̂̃��x���𑪒肵�A����̐H���ɑ��Ĕ��������邩�ǂ����ׂ܂��B����ɂ��A�̂��ǂ̐H���ɑ��ĉߕq�ɔ������Ă��邩����肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
▶���ӓ_�F
�x���^�t�[�h�A�����M�[�����Ɋւ��ẮA�ȉ��̓_���l������K�v������܂��F
1.�������ʂ̉��߁F
IgG�R�̂��������Ƃ��K�������A�����M�[�����������N�����Ă���킯�ł͂Ȃ����߁A�������ʂ̉��߂ɂ͐T�d�����K�v�ł��B��t��h�{�m�̏������Ȃ���A�H�������������Ƃ���ł��B
2.�ʂ̑Ή����K�v�F
�����Ŏ����ꂽ�H���ɑ��ĉߕq�����������ꍇ�A���̐H�������S�ɔ�����ׂ����A�ێ�ʂ�p�x�����邱�ƂőΏ��ł���ꍇ������܂��B�H��������邱�Ƃ����N���P�Ɍq���邱�Ƃ�����܂����A�ߓx�Ȑ������h�{�s���������N�����\�������邽�߁A��t�Ƒ��k���ĐH���������l�����邱�Ƃ��d�v�ł��B
3.�����̌��E�F
�x���^�t�[�h�A�����M�[�����́A���ׂẲߕq�ǂ�A�����M�[���������o����킯�ł͂Ȃ��A�������ʂ��K�������Ǐ�Ɉ�v����Ƃ͌���܂���B�Ǐ�̌��������̗v���i�Ⴆ�X�g���X����v���j�ɂ���ꍇ�����邽�߁A�����I�Ȑf�f���K�v�ł��B
�x���^�t�[�h�A�����M�[�����́A����̏Ǐ�ɑ��ĐH���̌��������s�������ƍl����l�ɂƂ��āA�L�p�ȃc�[���ƂȂ蓾�܂����A��t��h�{�m�Ƒ��k���A�T�d�ɍs�����Ƃ��K�v�ł��B
|
| �L�@�_�����Ƃ� |
|
�L�@�_�����iOrganic Acids Test, OAT�j�́A�A��p���đ̓��̑�ӏ�Ԃ𑽊p�I�ɕ��͂��錟���ł��B�L�@�_�́A�̓��̑�Ӄv���Z�X�Ő��܂�钆�ԎY���i����ӂ́g�����h�̂悤�Ȃ��́j�ł��B�A�ɔr�o����邽�߁A�A�͂��邱�ƂŁA�̓��̑�ӂ̏�Ԃ�h�{�̗��p�𐄑����邱�Ƃ��ł��܂��B
▶ �L�@�_�����ł킩�邱��
1.�G�l���M�[��Ӂi�N�G���_��H��TCA��H�j
���₷���A�X�^�~�i�s���̌������킩�邱�Ƃ��B
2.�_�o�`�B�����̑�Ӂi�h�[�p�~���A�Z���g�j���Ȃǁj
�����^���s���A�s���A�W���͒ቺ�ȂǂƂ̊֘A�B
3.�r�^�~���E�~�l�����̕K�v��
���Ƀr�^�~��B�Q�A�r�^�~��C�A�}�O�l�V�E���Ȃǂ̏��ՏB
4.�������i�ُ픭�y��J���W�_�̉ߏ葝�B�Ȃǁj
�����t���[���̃A���o�����X�A�ߕq�����nj�Q�Ƃ̊W�B
5.��Łi�̑��̃f�g�b�N�X�j�\�͂�_���X�g���X�̎w�W
�őf�r�o�����܂������Ă��邩���`�F�b�N�\�B
▶ �������@�F�@�A����
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�����I�Ȕ�J�⓪���ځ[���Ƃ���
�E�H���ɋC�����Ă���̂ɒ��q���ǂ��Ȃ�
�E�������̃g���u��������
�E�h�{�Ö@�̌��ʂ����ɂ߂���
�E���B��s���̖�肪����q�ǂ��̉h�{�ׂ���
|
| �~�l�����E�d���������Ƃ� |
|
���q�h�{�w�I�Ȋϓ_�ōs������t��A�̃~�l�����E�d���������́A�̓��̃~�l�����o�����X��L�Q�����̔r�������A���^�C���Ń`�F�b�N���邽�߂̕��@�ł��B���ꂼ��̌����ɂ͓����Ɩ���������A�є������Ƒg�ݍ��킹�Ďg���邱�Ƃ�����܂��B�i���@�ł͑��t�A�A�̌������{�s���Ă��܂��j
�@�������@�F���t
�E���́F���t�i�ʏ�͓���̏������ō̎�j
�E�ړI�F�̓��̃~�l�����o�����X�A���Ɏ��R�ɗ��p�\�ȃ~�l�����i�C�I�����~�l�����j�̓��I�ȏ�Ԃ�c��
�E���荀�ځF�i�g���E���A�J���E���A�J���V�E���A�}�O�l�V�E���A���A�����Ȃ�
����
�E���t�͌����̃~�l�����Z�x�Ƃ�����x���ւ����邽�߁A�����I�ȃ~�l�����̉ߕs���̔c�����\
�E�X�g���X��z�������o�����X�̉e�����₷���A�����_�o�̏�Ԃ̃q���g�ɂ��Ȃ�
�A�������@�F�A
�E���́F�A�i�����A or 24���ԔA�j
�E�ړI�F�̂���ǂꂾ���̃~�l������L�Q�������r������Ă��邩��]��
�E���荀�ځF�J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�i�g���E���A�J���E���A�����A�Z�����Ȃǂ̕K�{�~�l�����A����ѐ���A���A�q�f�A�A���~�j�E���A�J�h�~�E���Ȃǂ̗L�Q����
����
�E�A���ɔr�o�����ʂ́A�̂����̕������ǂꂾ�������E�r�o���Ă��邩�̎w�W�ƂȂ�
�E���ɗL�Q�����̃f�g�b�N�X�i�L���[�V�����j��̕]���ɂ��p������
�E�h�{�f�́u�����ʁv���킩��i���Ƃ��A�X�g���X�Ń}�O�l�V�E���r�o�������Ȃǁj
�B�������@�F�є�
�E���́F�є�
�E�ړI�F�����I�ȁi�ߋ��P~3�����j�~�l�������R��d����������c��
�E���荀�ځF�J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�i�g���E���A�J���E���A�����A�Z�����Ȃǂ̕K�{�~�l�����A����ѐ���A���A�q�f�A�A���~�j�E���A�J�h�~�E���Ȃǂ̗L�Q����
▶ �����ł킩���ȍ���
�@ �K�{�~�l�����i�h�{�f�j
| �~�l���� |
���� |
�s���ɂ��e�� |
| �J���V�E�� |
���A�_�o�`�B |
�s���F�C���C���A���e頏� |
| �}�O�l�V�E�� |
�G�l���M�[�Y���A�ؓ� |
�s���F���ނ�Ԃ�A��J |
| ���� |
�Ɖu�A�畆�A���_ |
�s���F���o��Q�A���X�� |
| �Z���� |
�R�_���A�Ɖu |
�s���F�Ɖu�ቺ�A�b��B�@�\ |
| �N���� |
�����R���g���[�� |
�s���F����ӈُ� |
�A �L�Q�~�l�����i�d�����j
| �d���� |
��ȓŐ��E�e�� |
| ����iHg�j |
�_�o�Ő��A�L���͒ቺ�A���X�� |
| ���iPb�j |
���B��Q�A�W���͒ቺ |
| �J�h�~�E���iCd�j |
�t���_���[�W�A����� |
| �q�f�iAs�j |
�畆�Ǐ�A��J�� |
▶ ���ꂼ��̌����̈Ⴂ�E�g������
| ���� |
��������e |
���� |
| �є� |
�����I�ȃ~�l�����E�����̒~�� |
�ߋ��̌X���i1~3���j�f |
| ���t |
���݂̑̓����p�\�~�l���� |
�z�������E�����_�o�̉e�����₷�� |
| �A |
�r�o�����~�l�����E�����̗� |
�f�g�b�N�X�\�͂�h�{�����̕]�����\ |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�h�{�Ö@��T�v�����g�p���Ă��邪���ʂ��s�\��
�E������J�E�W���͒ቺ�E���X���Ȃǂ�����
�E�L�Q�����̒~�ς��S�z�i����̐ێ悪�����A���ȋ������A���v���j
�E�H���ɋC���g���Ă��s��������
�E���B��Q��w�K��Q�̏���
�i�����ȋ����ɂ��s���̌������^����ꍇ�́A���̎��Ȉ�@�ւ̏Љ�������������܂��j
|
| ���t�R���`�]�[�������{DHEA�����Ƃ� |
|
�@���t�R���`�]�[������
�R���`�]�[���́A���t���番�傳���X�g���X�z�������ŁA�����ϓ��i�������A��Ⴂ�j������܂��B���t�����ł́A���t�Ƃ͈���Ĕ�N�P�I�ɃX�g���X�z�������̃t���[�i�����^�j���x���𑪒�ł���̂������ł��B
▶ �������@�F���t
�E1����4~6����t���̎�i���N������A�N��30����A�N��60����A���A�[���A�A�Q�O�Ȃǁj
�E���ꂼ��̎��ԑтɂ�����R���`�]�[���̃��Y�����O���t������
▶ �����ł킩�邱��
�E���t�̔�J�i�A�h���i���E�t�@�e�B�[�O�j
�E�����I�ȃX�g���X�ւ̔���
�E�����̎���T�����Y���i�̓����v�j�̗���
�E���ǁA�Ɖu�@�\�ւ̉e���̗L��
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�����I�Ȕ�J�₾�邳�������Ȃ��l
�E���N����̂��炢
�E�����ځ[���Ƃ���
�E�s���⑁���o��������
�E�X�g���X�����������𑗂��Ă���l
�E�X�N����PMS�Ȃǃz�������o�����X�̗���������Ă���l
�ADHEA����
DHEA�i�f�q�h���G�s�A���h���X�e�����j�́A���t�Ő��������z�������ŁA�R���`�]�[���ƃo�����X�����Ȃ��瓭���Ă��܂��B���z�������i�G�X�g���Q����e�X�g�X�e�����j�̑O��̂ł�����A�R�V���A�Ɖu�́A��ӁA�X�g���X�ϐ��ȂǂɊW���܂��B
▶ �������@�F
�E���t�܂��͑��t��DHEA�𑪒�
�E���t�R���`�]�[�������ƃZ�b�g�ōs�����Ƃ�����
▶ �����ł킩�邱��
�E���t����̃z����������ʁi�S�̓I�ȃX�g���X�ϐ��j
�E���z�������̑O��̂Ƃ��Ă̊���
�E�R�_���E�Ɖu�o�����X�̏��
�E�G�l���M�[�����͂̎w�W
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E������J��C�͒ቺ������l
�E����ɂ��z�������̕ω����C�ɂȂ�l�i40��ȍ~�̕��ɑ����j
�E�X�|�[�c��_�C�G�b�g�Ńz�������o�����X������Ă���l
�E�����s���A�X�N���Ǐ���l
▶ �R���`�]�[���{DHEA�Z�b�g�����̃����b�g
����2���Z�b�g�Œ��ׂ邱�ƂŁA���t�̃o�����X�i�����x�Ɖ́j�����ڍׂɕ]���ł��܂��B���Ƃ��A
�E�R���`�]�[�����l�{DHEA��l �� �����X�g���X�ŕ��t��J�̏���
�E�R���`�]�[����l�{DHEA��l �� ���t�@�\�̒ቺ���i�s���Ă�����
|
| �����t���[�������Ƃ� |
|
�����ɏZ��ł���ہi�P�ʋہE���ʋہE���a���ۂȂǁj�̎�ނ�o�����X�ׂ錟���ł��B�u�����ۑp�i���傤�Ȃ����������j�v�̏�Ԃ��������邱�ƂŁA�����E�z���E�Ɖu�E�����^���ȂǑ����̌��N��Ԃ̎w�W�ɂȂ�܂��B
▶ �������@�Ɠ��e
�E���́F��
�E��͂���鍀�ځF
�@�@- �r�t�B�Y�X�ہE���_�ۂȂǑP�ʋۂ̊���
�@�@- �咰�ہE�N���X�g���W�E���Ȃǂ̈��ʂ̊���
�@�@- �o�N�e���C�f�X���E�v���{�e�����Ȃǂ̊���
�@�@- ���_�Y���ۂ̊����i�Z�����b�_�̎w�W�j
�@�@- �����ۂ̑��l��
�@�@- ���ǂ⒰���V���Ɋ֘A�����
▶ �����ł킩�邱��
�E�����̋ۃo�����X�i�P�ʁE���ʁE���a���j
�E�֔�E�����E���Ȃ�E���r��Ȃǂ̌����̃q���g
�E���_�ۂ�r�t�B�Y�X�ۂ��L�x���i�������̗ǂ������j
�E���ǂ̃��X�N��얞�E���A�a�Ƃ̊֘A��
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�֔�≺���Ȃǂ̖����I�Ȓ��g���u��������l
�E�����̒���E�K�X�E���Ȃ�̏L�����C�ɂȂ�
�E���r��E�A�g�s�[�E�j�L�r�Ȃǔ��g���u��������l
�E�ԕ��ǁE�A�����M�[�̎��E���ȖƉu�����������Ă���l
�E���N�I���_�C�G�b�g�������l�i�����ۂő���₷����������j
�E�T�v���┭�y�H�i�������ɍ����Ă��邩��m�肽���l
�E���_�I�ɗ������݂₷���A�X�g���X�Ɏア�l�i���Ɣ]�͖��ڂɊW�j
�E40��ȍ~�̌��N�f�f����Ɂi���́u���̔]�v�u�V���̏o���_�v�j
▶ ������̊��p�@
�����t���[�������̌��ʂ����ƂɁA
�E�H�����̌������i�H���@�ہE���y�H�i�̎�ށj
�E�v���o�C�I�e�B�N�X�^�v���o�C�I�e�B�N�X�̑I��
�E�I�[�_�[���C�h�̒����v���������Ă���
�E�������̈������Ǐ�⎾���̌����ƍl������ꍇ�́A�����t���[���ڐA���������ڂ����������t���[���ڐA�����̍��ڂʼn��
|
| ���f�z���Ö@�Ƃ� |
|
���f�z���Ö@�́A���Z�x�̐��f�K�X�iH2�j��̓��Ɏ�荞�݁A���ʊ����_�f�i�q�h���L�V���W�J���j��I��I�ɏ������铭���𗘗p���āA���ʊ����_�f�ɂ��̂ւ̃_���[�W���y�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������Ö@�ł��B���f�͔��ɏ����ȕ��q�ł���A�ċz�ɂ���Ď�荞�ނ��ƂŁA���t�����߂���A�S�g�̍זE�ւƑf�����͂��܂��B
�̓��ʼnߏ�ɔ����������ʊ����_�f�́A�V���A������J�A�����K���a�A�e�퉊�ǐ������Ȃǂ̌����ƍl�����Ă��܂��B���f�z���Ö@�́A���Ƃ��ƈ�Ë@�ւŔ]�[�ǂ�S��~��P�A�̌������璍�ڂ���n�߁A���݂ł͔�J�A�������ǂ̌y���A�A���`�G�C�W���O�T�|�[�g�ȂǁA���L������œ�������Ă��܂��B
▶ ���Õ��@
1. ���f�K�X�z���Ö@
���Z�x���f���z��������@�B�������������B
��ÃO���[�h�̐��f�K�X�z���i��F1~4%���f�z���j�͓��Ɍ��ʂ������A���@�ł��Ē����鎡�Âł��B
2. ���Z�x���f�����T�v�������g�iHG�@EVO�@�G�C�`�W�[�G�{�j
�̓��Ő��Ɣ������A24���Ԃɂ킽�萅�f�������I�ɎY�����܂��B�킸�� 1g(3������)��800ml ���x�̐��f��24���Ԏ����I�ɎY�� ���܂��B�V�R�R������������GMP�F��H��Ő��������A���i���ȃT�v�������g�ł��B
���s��o�����ȂǁA���f�z����������ɂ����f�ێ悪�\�B
▶ ���f�z���Ö@�̓���
| ���� |
���e |
| ��N�P�I�i�̂ɕ��S�����Ȃ��j |
�z����T�v���ێ�݂̂ŁA�ɂ݂╉�S�͂���܂��� |
| �Z���ԂőS�g�ɍ�p |
1��30~60���̋z���őS�g�̍זE�ɐ��f���s���n��܂� |
| ����p���X�N�����ɏ��Ȃ� |
���f�͕s�v�Ȃ��͎̂��R�ɌċC��A����r�o����܂� |
| ���̎��ÂƂ̕��p���\ |
�����������ÁA���n�r���A���e��ÂȂǂƂ̑�����ʂ����҂ł��܂� |
▶ ���҂��������i�����A�Տ����j
| ���� |
���ʁE���� |
| �_���X�g���X�}�� |
�����_�f�����ɂ��זE�ی� |
| ��J�� |
������J�E���ӊ��̌y�� |
| �]�@�\�T�|�[�g |
�F�m�@�\�ቺ�A�]�[�nj�̉T�|�[�g |
| ���e�E�A���`�G�C�W���O |
�V���A���̂����݁A�V���h�~ |
| �ċz��T�|�[�g |
�x�@�\�ACOPD�ւ̃T�|�[�g�������� |
| ���Ǘ}�� |
�߉��A�������ǁA���ȖƉu�����ɂ����� |
| �����^���P�A |
�X�g���X�y���A�����̎�����ȂǕႠ�� |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E������J�⌑�ӊ������Ȃ��l
�E�W���͂̒ቺ�A�����̎��������Ɗ����Ă���l
�E�]�[�ǂ�S���ǎ����̊���������A�Ĕ��\�h���ӎ����Ă���l
�E���e�E�G�C�W���O�P�A���������l�i���̓�������n��UP�Ɂj
�E�^����̃��J�o���[�𑁂߂����A�X���[�g
�E�����K���a�i���A�a�A�������A�����ُ�ǂȂǁj�̗\�h�E���P��ڎw���l
�E�A�����M�[�������i�A�g�s�[���畆���A�b���Ȃǁj�̑̎����P����]����l
�E�F�m�ǂ�_�o�ϐ������i�p�[�L���\���Ȃǁj�̕⊮�Ö@���l���Ă���l
�E�a�C�ł͂Ȃ�����ǁu�ŋ߂Ȃ�ƂȂ����C���o�Ȃ��v�u�̂̔�ꂪ�����ɂ����v�Ƃ��������a�i�݂т傤�j��Ԃ̃P�A
|
| ���Z�x�r�^�~��C�_�H�Ƃ� |
|
���Z�x�r�^�~��C�_�H�Ö@�́A��ʂ̃r�^�~��C�i�A�X�R���r���_�j��_�H�ŐÖ����ɒ��ړ��^���鎡�Ö@�ł��B�����Z�x���ꎞ�I�ɍ����ێ����邱�ƂŁA�r�^�~��C�̍R�_����p��Ɖu�������A�R���ǁA�R��ᇌ��ʂȂǂ������o�����Ƃ��ړI�ł��B
▶ ���^���@
�E�_�H���ԁF��60~90��
�E���^�ʁF15~25g�A���Â̏ꍇ��60g�ȏ���g�p����邱�Ƃ�����܂�
�E�ʏ�͏T1~2��̕p�x�Ōp���I�ɍs���܂�
▶ �o���ێ�Ƃ̈Ⴂ
�r�^�~��C�͌o���ێ�ł͋z���ʂɌ��E������܂����A�_�H�ł͌����Z�x���o����20~50�{�ȏ�ɂ܂ō��߂邱�Ƃ��ł��܂��B
▶ ���҂ł������
| ���ʂ̗̈� |
���e |
| �R�_����p |
�����_�f�i�t���[���W�J���j���������A�זE�̎_���X�g���X��}�� |
| �����E���e���� |
�����j���̐����}���E�R���[�Q���������i�E���̓�����UP |
| �Ɖu�͌��� |
�E�C���X��ۂɑ���h���UP�i���ׂ⊴���Ǘ\�h�j |
| �R���Ǎ�p |
�߉���A�����M�[�Ȃǖ������ǂ̌y�� |
| ��J�� |
���t�T�|�[�g�A�G�l���M�[��ӂ̊������ɂ�薝����J�̉��P |
| �R��ᇌ��ʁi����̈�j |
���Z�x�ł̂����u����זE�̑I��I�A�|�g�[�V�X�U�����ʁv�����҂���A�⊮��ÂƂ��Ďg�p����邱�Ƃ�����܂� |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E���̃n���E���������A�b�v���������l
�E�X�g���X�E��J�����܂�₷���l
�E���ׂ��悭�����l�i�Ɖu���ア�Ɗ�����j
�E�������ǁA�A�����M�[���C�ɂȂ�l
�E�i���ҁE�A���R�[���ێ悪�����l�i�r�^�~��C�̏��Ղ��������j
�E�����a�▝������������l�i�זE�C���͂����߂����j
▶ ���ӓ_
�EG�UPD�����ǂ̗L���ׂ邽�߁A���Z�x�̃r�^�~��C�_�H���s���O�ɁAG�UPD�y�f�������K�v�i�n���̃��X�N����j�B
�E�t�@�\���ቺ���Ă���l�ɂ͒��ӂ��K�v�B
�E�_�H���ɓf���C�A���̊����A���C�Ȃǂ��ꎞ�I�ɏo�邱�Ƃ�����܂��B
|
| �O���^�`�I���_�H�Ƃ� |
|
�O���^�`�I���_�H�́A���͂ȍR�_�������u�O���^�`�I���v��_�H�ő̓��ɒ��ړ͂��鎡�Ö@�ł��B�O���^�`�I���͊̑��ō��������O�̃A�~�m�_�i�O���^�~���_�A�V�X�e�C���A�O���V���j����Ȃ�g���y�v�`�h�ŁA�̓��̉�ŁA�R�_���A�h��@�\��S���d�v�Ȑ����ł��B
▶ ���Õ��@
�E���^���ԁF1��20~30�����x�i�Ö��_�H�j
�E�p�x�F�T1~����i�̒���ړI�ɂ��j
▶ �O���^�`�I���̎�ȓ���
| ���� |
���� |
| �R�_�� |
�����_�f���������A�זE�̎_���_���[�W��h�� |
| ��Łi�f�g�b�N�X�j |
�̑��ŗL�Q�����i�d�����A�_��A�A���R�[���Ȃǁj�ʼn� |
| �Ɖu���� |
�������̋@�\���T�|�[�g�A�Ɖu�o�����X�𐮂��� |
| �����j���}�� |
�����E�̔��\�h�Ƃ��Ĕ��e�ɂ����p����� |
| �]�_�o�ی� |
�_�o�זE�̎_���X�g���X���y���i�p�[�L���\���a�₤��ɂ����ځj |
▶ ���҂�������
| ���� |
�K�� |
| ������J�E���ӊ� |
�����_�o�̗���A�_���X�g���X���֗^�����J |
| �A���`�G�C�W���O�E���e |
���̂����݁A�V���h�~�A�R�_�� |
| �̋@�\�T�|�[�g |
�A���R�[�����̏�Q�A���b�́A���̏�Q |
| �_�o���� |
�p�[�L���\���a�i�⏕�Ö@�j�AALS�i�����i�K�j |
| �������� |
������J�nj�Q�A���ۋؒɏǁA�A�g�s�[�Ȃ� |
| �A�����M�[���� |
�C�ǎx�b���A�A�����M�[���@���i���Ǘ}���ړI�j |
| �d�����~�� |
����A���A�_��Ȃǂ̉�ŃT�|�[�g |
| �R����ܕ���p�� |
�V�X�v���`���g�p���̐t�Ő��\�h�ɕی��K������i�����ی����ځj |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�V�~�E�����݁E�̔����C�ɂȂ��
�E��ꂪ�����ɂ����E���ӊ��������
�E�������悭���ށE�̑�������Ă����
�E�^�o�R�E�r�C�K�X�E�_��Ȃǂ̗L�Q�����ɂ��炳��Ă����
�E�X�g���X�������A�Ɖu�͂������Ă���Ɗ������
�E�����E�A���`�G�C�W���O��ړI�Ƃ������e��Â��������Ă����
▶ ���ӓ_
�E��r�I���S�ŕ���p�����Ȃ����Âł��B���X�̓��ɑ��݂��鐬���B
�E�H�ɃA�����M�[�����i���]�A����݁j���N�����ꍇ������܂��B
|
| �}�C���[�Y�J�N�e���_�H�Ƃ� |
|
�}�C���[�Y�J�N�e���_�H�iMyers' Cocktail�j�́A�r�^�~����~�l�������u�����h���ĐÖ����ɒ��ړ��^����h�{�Ö@�̈�ŁA��J�E�Ɖu�͌���E���������̃T�|�[�g��ړI�Ƃ��Ďg���܂��B
▶ ��{����
��ʓI�ɂ͈ȉ��̐������܂܂�܂�
�E�r�^�~��C
�E�r�^�~��B�Q�iB1�AB2�AB3�AB5�AB6�AB12�j
�E�}�O�l�V�E��
�E���̑��~�l����
▶ ���҂�������
| ���� |
���� |
| ������J�̉��P |
�זE�̃G�l���M�[��ӂ𑣐i���A�S�g�̂��邳���ɘa |
| �Ɖu�͋��� |
���ׂ⊴���Ǘ\�h�ɗL�� |
| �A�����M�[�ɘa |
�ԕ��ǁE�b���E����܂���Ȃǂ̏Ǐ�y���� |
| �Γ��ɁE�Г��ɂ̊ɘa |
�_�o�̉ߕq����}���� |
| �X�g���X�E�s���̃T�|�[�g |
�_�o�`�B�����̍����Ɋւ��B�Q��}�O�l�V�E�������艻 |
| ���r��E���e���� |
�r�^�~��C��B�Q�ɂ��R�_���E�畆�Đ��T�|�[�g |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�����I�Ȕ��E���ӊ��������l
�E�X�g���X�������A���_�I�ɂ��������݂₷���l
�E���ׂ������₷���E�Ɖu�������Ă���Ɗ�����l
�E�A�����M�[�̎��̐l�i�⏕�I�Ɂj
�E�Γ��ɂ▝�����ɂɔY�ސl
�E���̒��q�������E�A���`�G�C�W���O�ړI�̐l
�E��p��a��̉��̃T�|�[�g��
▶ ���ӓ_
�E���^�X�s�[�h����������ƁA�}�O�l�V�E���ɂ�錌���ቺ�E�ӂ���E�����E�M�����o�邱�Ƃ�����܂�
�E�t�@�\���������ቺ���Ă�����̓}�O�l�V�E���̔r���\�͂ɒ��ӂ��K�v
�E�r�^�~��B2�i���{�t���r���j�̉e���œ_�H��ɔA�����F���Ȃ�̂͐���Ȕ����ł�
�E�H�ɒ��ː����ւ̉ߕq�����i���]�A����݂Ȃǁj���o�邱�Ƃ�����܂�
�E�~�l�����̕ϓ��ɂ��A�ꎞ�I�ȓ��ɁA�f���C���o�邱�Ƃ�����܂�
|
| ���זE�㐴�t���ÂƂ� |
|
���זE�㐴�t�i�����ڂ����傤���������j���ẤA�l�R���̊��זE��|�{�����ۂɁA�|�{���̊��זE������o����鐶�����������i�������q�E�T�C�g�J�C���E�G�N�\�\�[���Ȃǁj��p�������Âł��B���̐������������͐g�̂̒��ɂ��銲�זE��Đ��\�͂̍����זE�ɓ��������A�g�D�̍Đ��𑣂��܂��B�i�����זE���̂��̂𓊗^���鎡�Âł͂���܂���B�j
���|�{�㐴�t�������ߒ���
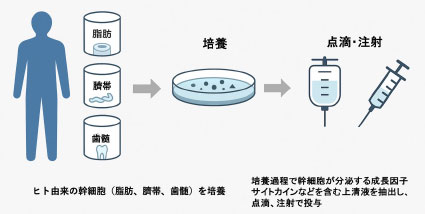
▶ ���҂�������
| ���� |
���e |
| �R���Ǎ�p |
�������ǂ�}���A�ɂ݁E�����y�� |
| �����i |
�g�D�̏C���E�Đ��𑣐i�i�畆�A�_�o�A���ǂȂǁj |
| �����E���e |
�V���A����݁A�V�~���P�A���̍Đ� |
| �_�o�� |
�F�m�@�\�E�]�_�o��Q�̉��i�i�����i�K�������j |
| �Ɖu���� |
���ȖƉu�����E�A�����M�[�����Ȃǂ̃o�����X���� |
| �̋@�\���J�̉��P |
����@�\���T�|�[�g��������� |
▶ ����Ȑl�ɂ�������
�E�����I�Ȕ���s����������l
�E���̂���݁E����E�����݂Ȃǔ��e�ړI�̐l
�E�g�̂���Ԃ点�����i�A���`�G�C�W���O�j�l
�E�ȉ��̂悤�Ȏ������������̐l�F�@���A�a�A�����̊̎�������ѐt�����A�����ُ�ǁA�������A������J�nj�Q�A�A�����M�[�A�Γ��ɁA�߂܂��A�@�ۋؒɏǁA�����u��
▶ ���זE�㐴�t�̎�ނƎg������
| ��� |
���� |
�������߂̗p�r |
| ���b�R�� |
�R���ǁE�Đ��͂����� |
���e�A�߉��A�̋@�\�T�|�[�g�A�A���`�G�C�W���O |
| �����R�� |
�_�o�����q������ |
�]�_�o�A�p�[�L���\���a�A�F�m�ǂ̗\�h�I�P�A |
▶ ���ӓ_
�E���Â��s���ۂ́A���җl�ƈ�t�Ƃ̍��ӂ̂��Ƃōs���܂��B��t��莡�Â̖ړI����S���A���X�N�A���ʂɂ��Ă�������Ɛ����������܂��B���a����������ɂ���ẮA���Â�����ꍇ������܂��B
�E���L�ɊY��������ɂ́A���Â��s���܂���B
1. ������ᇂ̊����̂����
2. �o���X���̂����
3. �D�P���A�D�P�̉\���̂�����A�D�P��]�̂�����A�������̕��i�����S���Ɋւ���G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j���s�����Ă��邽�߁j
4. 20�Ζ����܂���80�Έȏ�̕�
5. �{���Â̓��Ӑ��������̓��e�����������������Ȃ���
|
| ��Ȏ��ȘA�g�i���ȏЉ�j�ɂ��� |
|
�u��Ȏ��ȘA�g�v�͋ߔN���ڂ���Ă����Ñ̐��̈�ŁA�S�g�ƌ��o�̌��N�����ڂɊW���Ă��邱�Ƃ��Ȋw�I�ɖ��炩�ɂȂ��Ă������Ƃ���A��ȂƎ��Ȃ̘A�g�ł̎��Â����߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�ȉ��ɁA�ߔN�̈�Ȏ��ȘA�g�̔w�i�E�ړI�E��̓I���������������܂��B
▶ �Ȃ���Ȏ��ȘA�g���K�v�Ȃ̂��H
�����o�ƑS�g�̌��N�́u�o�����v�ɉe�����遄
| ���o�̖�肪�S�g�ɋy�ڂ��e�� |
�S�g�̎��������o�ɋy�ڂ��e�� |
| �����a �� �����d���A���A�a�����A���Y |
���A�a �� �����a���� |
| ���o���� �� �뚋���x�� |
�Ɖu�ቺ �� ���o�J���W�_�� |
| ��Q �� �h�{��Q�E�T���R�y�j�A |
���� �� �������A���o���� |
| �`���s�� �� ������Q �� �뚋 |
���_���� �� ���o�P�A���� |
����l�̊��҂̌��N���I�Ɏ��ɂ́A��t�Ǝ��Ȉ�t�̘A�g���s���ł��B
▶ ��Ȏ��ȘA�g�̋�̓I�ȖړI
1. �S�g�����̎��Ì��ʂ��ő剻����
2. ����҂̌뚋���x���E��h�{�E�t���C���̗\�h
3. ����ҁE���҂Ȃǂ̎��p���E�ɘa�P�A�̎x��
4. �����K���a�Ǝ����a�̓����Ǘ�
▶ �ߔN�̈�Ȏ��ȘA�g�̎�Ȏ��{��
1�D���p�����o�@�\�Ǘ��i����E���`�O�Ȏ�p�Ȃǁj
�E�p�O�Ɏ��Ȃ���� �� ���o�ۂ����炵�ďp�㍇���ǁi�x���A�����j��\�h
�E�ی����ڂ���Ă���A���_�a�@�Ȃǂŕ��y
2�D���A�a�Ǝ����a�̑��݊Ǘ�
�E�����a���Â�HbA1c�i�����l�j���P�Ɋ�^���邱�Ƃ�����
�E���ȂƎ��Ȃ���L���A�o�����玡�É��
3�D�뚋���x���̗\�h�i�ݑ�E����Ҏ{�݁j
�E���o�P�A�̓O�ꂪ�x�����X�N��ቺ
�E��t�A�K��Ō�t�A���ȉq���m�A�Ǘ��h�{�m�Ƃ̘A�g�̐����d�v
4�D�t���C���E�T���R�y�j�A��
�E�E�����@�\�ቺ �� ��h�{�E�ؗ͒ቺ�̈��z�ɂȂ���
�E���Ȃ͋`���E�@�\�̉��P�A��Ȃ͉h�{�E�^���w�����s��
���o�͑S�g�̋��Ƒ����A�S�g�����̎��Â�\�h�̈�Ƃ��Ď��Ȏ��Â����p���鎞��ɂȂ��Ă��܂��B��ȂƎ��Ȃ��A�g���邱�ƂŁA
���a�C�̎��Ì��ʂ����܂�
���Ĕ��\�h�E���N�����̉��L�ɂ��Ȃ���܂��B
|
|
|